宇宙状況把握(SSA: Space Situational Awareness)においては、光学カメラによる観測と並んで、電波による位置や速度の推定が重要な要素です。日立製作所 研究開発グループは、2024年には宇宙状況把握の高精度化をめざし、全方位からの電波を観測して電波源を特定する基本技術を開発しました。2025年には、宇宙からの災害監視・インフラ管理の精度を高める「構造化電波」技術の原理検証に成功。宇宙状況把握と構造化電波の技術開発に携わってきたNext Research 宇宙プロジェクトの田部洋祐主任研究員と木村寿利研究員に、取り組みの経緯から今後の社会実装まで話を聞きました。
音の研究者と宇宙放射線の研究者の日立での出会い
田部:昔から「音」に興味があり、大学は音響設計学科に入学、芸術工学を専攻して博士を取得しました。声帯が振動して流れに渦が発生し、それが声帯と相互作用して声に変わるまでを解明する基礎研究です。その頃は、何かに役立つということよりも、単に音や声に対する興味を追求していただけでした。そのような関係から、音声関連の基礎研究ができる研究所にエントリーしましたが、採用にはいたりませんでした。そんなときに担当教官から、「日立なら音の研究ができる」とアドバイスを頂き、博士号取得者の入社にも門戸を開いていて、音の研究もできる、ということで2007年に日立に入社しました。

日立製作所 研究開発グループ Next Research 主任研究員・田部洋祐
入社後は、茨城県勝田市にあった機械研究所(現在は研究開発グループに統合)へ配属されました。最初のテーマは油圧ショベルなど建設機械の低騒音化でした。その後も自動車機器や鉄道車両の静音化など、音環境に関する研究にずっと携わってきたのですが、やがて環境そのものへと関心の幅が広がり、自然資本勘定に興味を持ち始めました。これは宇宙レベルで地球を観察することで、森林や土壌、水や大気、動植物や鉱物資源などの自然資本が持つ経済価値を考える学問なのですが、ちょうどその頃に宇宙にかかわる研究開発の社内公募があったので、迷わず応募して現在に至る、というわけです。
木村:私は応用物理学専攻で修士課程を修了しましたが、研究室では国際宇宙ステーションの日本実験モジュールの船外実験プラットフォームに設置し、宇宙放射線を検出する装置の性能評価に取り組んでいました。国際協調や宇宙ステーションといったスケールの大きな研究が好きだったんです。就職活動では宇宙そのものはそれほど意識せず、当時注目されていた自然エネルギーを使った発電を軸に考えていました。仕事をするとなったら、人々の生活を支えているインフラ系で役立ちたいとの考えからです。その中でも電気が生活に根付いている実感が強く、また資源が少ない日本では自然エネルギーによる発電が喜ばれると思ったのです。

日立製作所 研究開発グループ Next Research 研究員・木村寿利
調べてみると日立だけが自社オリジナルの風車(風力発電機)を作っていたので、日立に2015年に入社しました。入社後は、風力発電所の電気設計を担当していました。高圧の受電盤や開閉器盤などのシステム設計です。その後、ビジネスの方針転換があり、他にチャレンジできることはないかと考えていたとき、宇宙太陽光発電所の研究テーマで社内公募を見つけました。発電と宇宙なら、やらない手はないと手を挙げ、ここで田部さんと合流することになります。
宇宙太陽光発電から宇宙環境把握へ
田部:木村さんが言及した通り、宇宙関連の研究開発は、当初、宇宙太陽光発電がメインでした。宇宙空間に太陽光パネルを張り、受けた太陽光の電力を電波として放射して地球に送るものです。実現のため、打ち上げるときはパネルを小さく折り畳み、宇宙空間で大きく広げて発電するための薄膜衛星の研究をしていました。しかしこの研究は実現までに長い年月がかかります。そこで、薄膜を宇宙で展開する技術を使ってなにか違う形の研究提案ができないかと考えました。そこで生まれたアイデアが宇宙観測でした。薄膜を張った衛星で電波を観測して、宇宙の状況を把握しようというものです。

木村:宇宙の課題として、宇宙空間に衛星などさまざまな物体が打ち上げられていて、混雑化が懸念されていました。そこで、宇宙状況を宇宙空間に打ち上げた衛星から把握するための研究開発を始めました。一般的な宇宙状況把握(SSA:Space Situational Awareness)は、地上からレーダーや光学望遠鏡を使って観測しています。この方法では、ある1区画しか観測できず、観測できる範囲が狭いという課題がありました。しかし、宇宙空間に打ち上げた衛星からSSAを実現できれば、衛星の周囲全体の状況をマッピングすることが可能になります。全方位観測衛星を作ろうというわけです。他の衛星やスペースデブリ(衛星やロケットの破片などの不要な人工物)などから守りたい重要な衛星の近くに従衛星(co-satellite)を打ち上げて全方位を観測することで、妨害する物体や危険な物体の存在を監視できるだろうというものです。

田部:さらにその先では、自律的な衛星でSSAを利用することも考えました。機能を持った衛星自身がSSAも実施して、障害物を検知したら回避行動を取ることにつなげられます。
木村:論文などを見ると、衛星がデブリなどの近接に対して回避行動を取ることはあるようです。デブリはたとえ1cm大のものであっても、秒速数kmで飛んでいますから衛星に衝突すると大きな破壊力があります。破壊によってデブリそのものがさらに増えてしまうことも避けたいので、衛星からのSSAによって障害物との衝突を避けることは大きな社会的な意義があるのです。
田部:宇宙空間での衛星の高密度実装は、現在は特定の高度の軌道上に配置する形で進められています。しかし、3次元的な軌道を持つコンステレーション(satellite constellation)、すなわち立体的な配置も提案されています。今後も衛星は増え、動きも複雑になるとしたら、全方位からものを見て自律的に動けるようにする技術は必要不可欠です。宇宙機から、全方位で刻々とした変化に対した状況把握ができれば、地上から限られた範囲を観測する現行のSSAとは全く異なるアプローチとしての利用が可能になります。
テンセグリティ構造で宇宙空間に薄膜を展開
田部:打ち上げた宇宙機から、全方位の観測を可能にするためには、アンテナを宇宙機の周囲に全方位に展開しなければなりません。打ち上げるときは小さく、宇宙空間に打ち上げてから全方位に広く展開する必要があるのです。ここで、テンセグリティ(tensegrity)構造という特殊な構造の適用を思いつきました。

衛星軌道上で展開するテンセグリティ構造3次元アレイアンテナ(イメージ)
宇宙船地球号(Spaceship Earth)を着想したことで有名な建築家のバックミンスター・フラー(Buckminster Fuller:1895‐1983)が考案したテンセグリティ構造は、張力材と圧縮材を組み合わせて、膜を全方位に向けて張ることができます。大学生の頃から知っていた構造ではあるのですが、宇宙機の周りに小型軽量で展開するアンテナ構造が求められたときに「これだ」と思いつき、研究に適応してみました。
木村:衛星では、電力供給のための太陽光パネルを畳んで打ち上げ、宇宙空間で広げる方法を使っていることはよく知られているでしょう。でもパネルは硬くて重いのです。SSAに使う宇宙機では、全方位にアンテナを張るために軽量化も求められるので、薄膜を張ることを考えました。
田部:テンセグリティ構造によるアンテナは、全方位の把握について音波を使って実証を行いました。電波と音波の間には相似則があり、ある周波数の電波の振る舞いを、低い周波数の音波で相似的に測定できるためです。学生時代の声の研究で、電磁気と音響のアナロジーを取り扱ってきたので、理論の検証についてまずは音波を使って評価することにしました。

音波を用いてテンセグリティ構造によるアンテナで全方位の空間把握を実証したところ、横軸の0度から360度まで、縦軸の0度から180度までの全ての空間で、受信した音波から周辺に配置した物体の位置をマッピングできることがわかりました。全方位の空間把握が音で可能なことを実証できたことから、相似則によって電波でも同等の効果が得られるという原理の検証ができたのです。

発信源の方向を3次元的に特定可能な回転電波干渉方式の原理検証
木村:私は、音波で原理検証ができた上で、実際に電波で検証する部分を担当しています。音波では田部さんの話のように、全方位で物体を測定できることがわかりました。実際に使用する電波領域ではどのようなふるまいを示すのかを実験で確認します。電波実験では電波の周波数が高く、実験環境や装置状態の影響を比較的受けやすいため、音波のようにきれいなデータを計測するのが難しいです。それらの影響を一つずつ紐解きながら、全方位の空間把握を電波でも証明していきたいと考えています。

田部:テンセグリティ構造で3次元空間把握の確認ができた一方で、研究の方向性が変わってきていることも事実です。テンセグリティ構造のアンテナで3次元空間把握をするときには、どこかから飛んできた電波を受けて障害物などの存在を把握するわけですが、これはパッシブな電波の取り扱いです。最近は、自ら電波を出して対象物から跳ね返ってくる電波を観測する、アクティブな測定の方法に研究がシフトしています。パッシブな電波の測定よりも、よりリッチな情報が取得できるはずと期待しています。
特殊な「構造化電波」を使って時空の状況を把握へ
田部:アクティブな電波として、「構造化電波」という特殊な電波を研究対象に取り上げました。偏波状態や位相、周波数、電波の形などを自由に制御して作り上げた電波を発することで、反射波を使って対象の状況を調べる方法で、レーダーと同様の考え方です。宇宙の状況把握から、宇宙からのセンシングデータを使った地球の観測という、研究テーマに新たに取り組んでいます。
私たちが開発している構造化電波は、螺旋の波面を持つ電波を重ね合わせて作ります。構造化電波を利用することで、地球観測でよく使われているレーダーの画像が2次元的なのに対して、歪みのない3次元の画像が得らえると考えています。また、この螺旋の波面は壊れやすく、大気中を伝搬していく過程で波の形が崩れていきます。すなわち、大気に対する感度が高いということであり、崩れの度合いを分析することで空間的な情報も分析できます。構造化電波を使うことで大気に対する空間的な情報を得られれば、天候の状況や気候変動などを空間的に把握できるのです。もちろん、感度が高いということは、送信して反射した電波を受信するまでのハードルが上がることでもあります。どのように送受信したら良い応答が得られるか、また、それをどう分析するかなど技術課題が多く残ります。それでも新しいことに挑戦していると、面白く楽しいです。
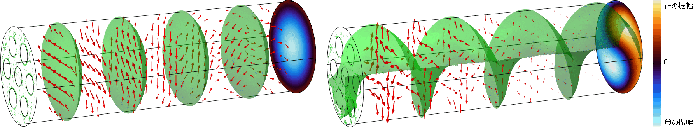
従来の平面波(左図)と、今回開発した構造化電波(右図)の比較(緑色:波面、矢印:電界ベクトル、右端のカラーマップ:電界の正負の振幅)
木村:これまでにも宇宙空間から地球観測はさまざまな形で行われてきました。今回、日立として構造化電波を使って地球観測しようとしたとき、我々の強みはどこにあるかと考えたのですが、新しい情報を取得し、それを従来蓄えてきた日立の知見と組み合わせることで、新しい価値に変換できる可能性があるということに気がつきました。新しい情報としては、例えば、電波が空間的な分布を持っているため、見ている平面上を動く物体に対しては、空間情報を使えば速さがわかるということなどを挙げることができます。3次元の情報からは動く方向もわかるでしょう。そして2025年には構造化電波の原理の検証にも成功しました。
これまで発電所の設計として数十Hzといった周波数を対象にしていたのが、今は数十億Hz(GHz)の電波を扱うことになり、スケールも挙動も全然違うので、実験しながらデータを解析している最中です。電気だけの知識では解けないことも多く、大気との干渉に関しては統計学的な知識などが求められます。実験装置自体は市販の製品を使っていますが、原理や信号処理などについても学んでいるところで、常に勉強の必要性をと感じています。

田部:電波を使ったセンシングを実現するためには、木村さんと同様に勉強することがたくさんあります。理論を構築してシミュレーションで実現できたと思っても、実際に実験してみると考えもつかなかったことが起きることが多々あります。実証することが本当に大事なので、一歩一歩、木村さんやほかのメンバーと一緒に実証を進めていきます。
都市インフラの監視や環境モニタリングへの適用をめざす
木村:構造化電波の社会実装のメインとして考えているのは都市インフラの監視や環境モニタリングです。都市インフラは労働人口が減少するにつれ監視が行き届きにくくなりますが、宇宙からの監視で広範囲にインフラのデータを取得できれば、インフラの老朽化をいち早く見つけ、安心安全な暮らしを提供できるのではないかと考えています。また、地球温暖化などに対応する社会を作るために、従来は過去のデータから予測していましたが、構造化電波を使えば宇宙からのリアルタイム情報を基にした環境モニタリングで、環境の状態を予測することができるようになります。このように日々変化する環境に対応していける社会が作れたらいいと考えています。

構造化電波を利用した地球観測のイメージ図
田部:構造化電波は、「空間情報」という新しい次元を導入できます。電波は、これまで周波数や振幅、位相、垂直・水平偏波などの次元で情報をやり取りしてきました。それに空間の形という次元が加わることで、考え方の枠を増やせるのです。例えば通信ならば、構造化電波によって空間情報を取り入れることで、さらに伝達できる情報量を増やすことにつながります。センシングでも、これまで見えていない情報を使うことで、アクティビティの領域を広げていけるでしょう。
電波は、ある空間の中で反射や干渉をしながら、空間的な構造を持っています。その波の空間情報を分析することで環境の把握がより高度に実現できるでしょう。現在、構造化電波として利用している渦も空間モードの1つです。これ以外にも波には多くの空間モードがあり、それらを構造化電波に取り込むことで空間を把握できる領域を広げていけると考えています。
木村:私たちが取り組んでいるこのプロジェクトでは、さまざまな機関との共同研究を推進しています。特にJAXA(宇宙航空研究開発機構)や東京大学との連携が大きいですね。日立には社内に幅広い分野の専門家がいるのは確かですが、宇宙は新しい事業領域なので、社外と連携することに大きな価値があると感じています。
田部:実は、宇宙専門の事業部である宇宙技術推進本部が過去にはありましたが、組織を廃止してから時間が経過したこともあり、社内に宇宙に関する知見を持っている人が少なくなってしまったのです。今の部署では宇宙に関してはゼロスタートのような状況で、立派な研究機関や先生方に引き上げてもらって、学会発表もさせていただいたこともみなさんのおかげだと思います。
木村:そうした協力を仰いで、宇宙での実証を7年後に実施することをめざしています。構造化電波の特性がセンシングに結びついていくと、面白いことができそうだねと言えるようになりたいです。
田部:宇宙実証の前に、まずは航空機を使った実証を計画しています。地上での実験と、航空機での実証を通じて、構造化電波の使い方や処理の仕方の提案ができるようになると思っています。なるべく早く皆さんに情報を公開、共有し、連携機関と議論して活用の可能性を考え、早く社会に価値を問うていきたいです。

田部洋祐(Yosuke TANABE)
日立製作所 研究開発グループ Next Research
宇宙プロジェクト 主任研究員
クオリティとは何かを考え続けるきっかけの一冊
「禅とオートバイ修理技術」(ロバート・M・パーシグ著、早川書房)は、父と息子がオートバイで全米を旅しながら、クオリティの本質について考えていく、旅の記録と哲学的思索が融合した書籍です。旅の途中でオートバイを修理したり、過去の記憶を思い出したりする中で、理性と感性の対立や、それらを調和させるクオリティのあり方を思索していきます。学生時代に友人に勧められて読んだのですが、常にクオリティとはなにかを考えさせられるので、今でも読み返しています。芸術工学専攻だった学生時代から、芸術と工学の両方に携わっていましたが、この本でも芸術と工学の融合が重要なテーマの一つです。この本で感じたように、クオリティを追求し、最先端(State-of-the-Art)の研究開発ができると、幸せだなと思っています。

木村寿利(Hisatoshi KIMURA)
日立製作所 研究開発グループ Next Research
宇宙プロジェクト 研究員
ものづくりについて常に学ぶということ
書籍としては、「図解 誘導電動機: 基礎から制御まで」(坪島茂彦著、東京電機大学出版局)が印象に残っています。発電機や電動機の理解に役立つ本です。誘導電動機の組立工場で実習があったとき、作業をしていた上長がこの書籍を読んでいました。日立では研究者や設計者、作業者などの分業が進んでいますが、組み立ての現場の方も設計者が知るような技術を把握する学びを続けていることを知り、そのラストマン精神に感動しました。
もう1つは「風車つくり工房 」というYouTubeチャンネルです。元の部署の上司が立ち上げたもので、ご自身で発電する風車を作ろうと取り組んでいる内容を動画で紹介しています。電気構造編、機械構造編など、日立ならば課になるレベルの内容があります。副業制度も利用して進めているものであり、こうして学び続けている人がいることが日立の良いところだと改めて感じています。
(撮影:服部 希代野)













